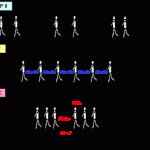「設備を増やさずに生産量を10倍か~」
学生の時からOR(オペレーションズリサーチ)とかゲーム理論とかが大好きで、会社にナイショで勝手に最適化ソフトウェアとかプロジェクト管理ソフト(MS-Project)とかを自腹で買って持ち込んで仕事をやっていたような私は、
「これは面白いプロジェクトかも」
と、何故かできる気になってました。
10倍は最適化とかで何とかなるようなレベルではないんですけどね。
若かったからかな。

ひとまず開発品を試作してエンジンテストとかに送らないといけないので、会社で指定されているプロジェクトスケジュール管理方法はまるっと無視して、1人でナイショでMS-Projectを使って治具手配、工具手配、加工設備の手配などのクリティカルパスを管理しながら開発試作プロジェクトををビシっと垂直立ち上げしました。
なんでナイショで使うかというと、自分独自の手法でやっているのがバレると、会社で指定されているプロジェクトスケジュール管理方法(詳細は伏せておきます)でやらされてしまうからです。
どんなに良いものでも決められたスタイルじゃないとみんなが使えないから、みんなが使えるヤツにしましょうという意図です。
もちろんそれも分かるんですけどね。
ずっとナイショもアレだし、何度か上司やスケジュール管理の部署に「MS-Project便利だから使いましょう」と言って試してもらいましたが、なんか良く分からん的な感じで、「やっぱこれだねー、Excel最高」と会社指定のヤツに戻ってました。
クリティカルパス法でプロジェクト管理するコツは、ただ単にクリティカルパス上にいる人たちに「もうすぐ来るからお願いね」とタイミング良く声を掛けていくだけです。
MS-Projectはスケジュールが思い通りにならなかった時に、クリティカルパスが即座に演算できるというだけの大したことないソフトウェアです。
この頃から、
「シマダはいつも簡単に立ち上がるプロジェクトばかり担当してて運が良いな~。そういう簡単なヤツやりたい。」
と言われるようになってきました。
まったくそのとおりだな、と思います。
簡単なものばかりで運が良かったですよ、ホント。
わたしは生産技術の仕事をする上で、機械加工の技術では、ほとんど迷いがありませんでした。
私が物心つくまえから父が鉄工所(シマダ機工)を経営しており、小さい頃から鉄工所の中を遊び場にしていて機械加工に慣れ親しんでいたっていうのが大きいと思います。
夏休みとかの長期休みは実家の工場(コーバと読みます)でアルバイトしていて、汎用フライスで6Fしたり、汎用旋盤使ったり、NC旋盤ポチポチしてました。
すごい幼少期に単能機でヤマハのボートのなんかのカップリングを加工してた記憶もありますよ。
コーバで手伝ったり、チョロつくのはとても楽しかったです。
三菱重工に居る時はなんか実家が鉄工所というのが言い出せなくて、ナイショな話でした。
また学生時代は、父の意向なのか母の意向なのか、なぜかお小遣いが無制限システムになってて本が買いたい放題でした。
月に5万円くらいのけっこうな量の本を買っていて、学校の図書館の本もあわせて読んでいたので、学生時代にたくさんの基礎学習ができたものと思われます。
父と母にとても感謝してます。
話を戻して、さらに別のシーンに移りますが、三菱重工のわたしが居た部署は、若手の教育にチカラを入れているところでした。
研修メニュー的なものが定期的に回覧されてきて、希望すると様々な研修に参加することができました。
実験計画法とかシーケンサの使い方とか、なんか節操が無い感じでかなりたくさん受講していました。
くだんのリコールの開発試作品は上手く立ち上がってはいましたが、問題は量産時の生産量をどうするか、でした。
物理的な制約があるものを攻略する何か良いヒントはないかな、と思って生産性アップ的な研修に申し込みました。
たぶん「統計的なんとか手法で生産性をアップしよう!」とか、そんなヤツです。
タイトルからして生産量10倍は無理そうですけど。
なんで生産性をアップしたいのか、という参加目的を研修の始まりの時にプレゼンするのですが、
「設備を増やさずに生産量を10倍にしよっかなと思ってて」
と言ったら講師(三菱重工の他事業所の生産技術職の主任だったような記憶があります)の人が目をキラキラさせて盛り上がり、「こんな本があるよ、読んでみなさい」と黄色くて分厚い本を手渡してくれました。
それが今ではとても有名な、ザ・ゴールという本でした。コミック版もあり。
講師の人は元々のカリキュラムにはあんまり沿わず、ザ・ゴールがいかに素晴らしい本であるかをチョイチョイ語るというナゾな研修になりました。
「統計はどこ行っちゃったんだよ、ワカバヤシ先生」
と印象が強かったせいか、講師の名前まで覚えてます。
これがわたしとTOCとの初めての出会いなのでした。
つづく。
このシリーズの記事リストはこちら。
・TOC思考プロセスとの出会い編 (1) 三菱重工時代に困難に直面
・TOC思考プロセスとの出会い編 (2) 三菱重工時代に研修でTOCをチラ見する
・TOC思考プロセスとの出会い編 (3) シマダ、会社でTOCを使うってよ
・TOC思考プロセスとの出会い編 (4) 平社員がTOCを会社で使ってみる件
・TOC思考プロセスとの出会い編 (5) みんなで頑張る